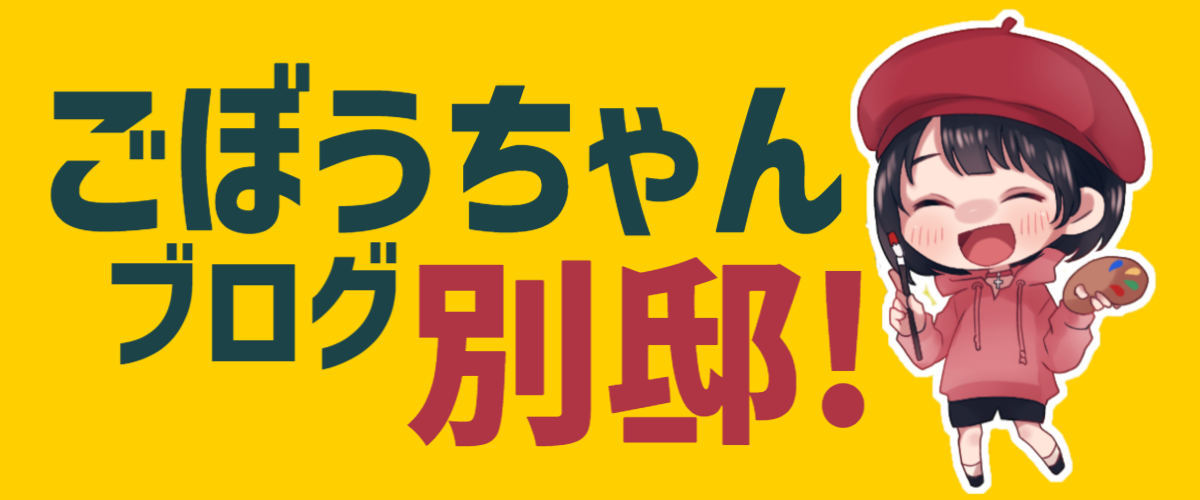日本の文化財保護の基礎を築いた彫刻家として知られる新納忠之介を紹介します。
***
こんにちは。人から分かる3分美術史。
今日は新納忠之介について勉強していきましょう。
新納忠之介。1869年生まれ。日本の文化財保護の基礎を築いた彫刻家として知られます。
明治元年、新納は鹿児島市に生まれました。同じく鹿児島出身の画家である床次正精に絵画を学んだのち、1889年、東京美術学校彫刻科に入学します。
学校で彫刻を高村光雲、美術史を岡倉天心に学びます。また、同期には板谷波山がいました。
新納は若くして頭角を現し、光雲らによる楠木正成像の制作に参加。
新納の卒業制作が、「渡海達磨像」です。写実的な仏像でありながら、土台の波の描写などに独自の創作性があります。
当時、廃仏毀釈の政策と、西洋との貿易政策により、仏像をはじめとする日本の古美術は破壊や海外流出の憂き目に遭っていました。
そこで新納は、天心から文化財保存事業への従事を命じられます。新納は当初「華やかならぬ仏像修理作業に就くことは此世から葬られる」とも考えましたが、その事業をやりとげることとなります。
1897年には「古社寺保存法」が成立。現代まで続く「国宝」指定など、文化財保護のための法令が整備されました。そして、古社寺保存法に基づく最初の事業となったのが、「模造中尊寺一字金輪坐像」です。中尊寺金色堂に蔵されていた平安期の秘仏を、新納が模作しました。
新納の仕事を見ていきましょう。
「東大寺法華堂 不空羂索観音像」。1906年、37歳の新納が修理に従事しました。岡倉天心が主導した「現状維持修理法」に基づく最初の作例であり、日本の近代的な仏像修理方法の端緒となった作例でもあります。
「蓮華王院三十三間堂 千体千手観音立像」。1936年、67歳の新納を中心に、1001体に及ぶ千手観音像の修理事業を開始。新納の死の2年後である、1956年に完了しました。
1954年、新納は87歳で亡くなります。それまでに2600体以上に及ぶ文化財修理を行い、日本の文化財保護の基礎を築いたのでした。
以上!